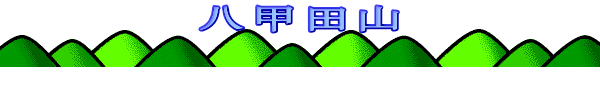
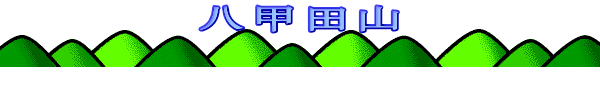
岩木山未登頂の翌日、まだ雨模様の朝八甲田山に向かって一人歩き出す。昨晩大勢の宿泊客がいた酸ヶ湯温泉だが、出発時午前6時半は登山客は誰もいなかった。また今日も一人旅かと思いながら行く。
今回は最初から雨でカッパ着用したら道中汗が吹き出てきた。登山道が狭く両側の枝葉が体に当たり、肩から下げたカメラまで全身濡れる。実に不快な感じが続く。
やがて火山危険の標識が出てきた。まもなくあたり一面が山火事があったかと思われる場所に出た。
噴煙こそないがそこは新しく噴気が出て木を枯らした場所であった。硫化水素だろうか硫黄の匂いがきつく、急いで通りすぎる。
暫く、ミズナラとダケカンバの茂った登山道で、あたりは霧に包まれおり視界は全くなく薄暗い状態が続く。
一時間を過ぎると硫黄の匂いのする地獄沢に出た。視界は少しは良くなったが、硫黄で黄ばんだ岩石がゴロゴロしている所を一人登る。地獄沢にふさわしい所だ。
まもなく仙人岱(せんにんたい)という木道のある湿地帯に出た。ここには木の枡で囲んだ水場があり、ベンチがあった。
雨が止んで霧雨になったため、一人ベンチで宿でもらった朝食弁当を食べる。
あたりは濃いガスで視界は悪い。人影もなく不気味だ。天気が良ければ大勢の登山客がいるところだろう。
ここは高山植物の宝庫だそうだが、八月下旬ともなると花も終わりに近い。よく知っているチングルマ等はない。
それでも咲いている花を見つけるとパチリとする。
湿地帯を過ぎ急登になると、まもなく「鏡沼」という小さな池に出る。噴火口の跡だろうか。また雨が降ってきた。ますます濃くなったガスの中、上りの急登が続く。両脇はハイマツのようにアオモリトドマツが群生している。冬になると、蔵王と同じ見事な樹氷が見れるところだ。
急登で足が重くなった頃、初めて一人の若い登山客が追い越していった。こんな日でも登る人がいるもんだと、勝手に思いながら、なぜかホッとする。
登り始めて三時間を過ぎた頃、八甲田山頂上の広い大地のような「大岳」に到着。視界は相変わらず悪い。先ほどの若い登山客が食事していた。横浜からバイクできたという。郷里の北海道から山を登りながら南下すると言っていた。
若い登山客が下山して、濃い視界の全くない頂上で一人になった。今まで頂上には必ず複数の登山客がいるが、ここは違った。
せっかくだから頂上の周りに生えている高山植物をいくつか写真を撮る。
いよいよ下山しようかと支度をしたら、年配の御夫婦が上がってきた。茨城からきたという。昨日はものすごい風と雨で、頂上直下で引き返し、再度登山したのだという。昨日は青森の山はどこも荒れてたらしい。岩木山の未登頂もやむを得なかったのだ。
天気の悪い中、登山するのは、山をハシゴする人たちだけなのか。自分はなぜこんな馬鹿なことをするのだろうとフッと思った。
御夫婦を残し先に下山し始める。
まもなく反対側から一人の登山客が登ってきた。今日で二人目だと独り言をいって通り過ぎた。今日の八甲田の登山客は3〜4人しかいなかったのではないかと思った。
大岳避難小屋を過ぎ、再び湿原に出た。上毛無岱という。木道が一直線に伸び、それが霧の中に消えている。この辺は高山植物が終わりで、ナナカマドが色付いており、もう秋の香りがする場所であった。秋には尾瀬の様に草紅葉が見事だという。残念ながらその全貌は見れなかった。再び階段状の登山道を下る。またもや平坦地の湿原に出る。下毛無岱である。所々に池塘が有り、湧水が流れ込む木道を通る。景色は良くなくても平坦な木道は歩きやすく、足も快適になる。
途中湿原の中に休憩ベンチがあるが頂上の大岳方面の視界は全くない。
酸ヶ湯温泉を出て、頂上の大岳を一周し再び酸ヶ湯温泉に戻るコースは五時間で終わった。
雨が降ったり止んだり、視界の全くない登山であった。
昨日は広島で土砂災害で70人もの死者・行方不明が出た豪雨があったらしい。東北も同じ低気圧の前線上にあり、天気は暫く良くないようだ。
写真をクリックすると大きくなります。



酸ヶ湯温泉 八甲田登山口 火山標識



荒涼とした噴気跡 八甲田連邦 地獄沢



噴気標識 仙人岱湿原 鏡池



アオモリトドマツ 八甲田(大岳)頂上 広い大地の頂上

毛無岱湿原



ノリウツギ キリンソウ ヨツバシオガマ



ツリガネニンジン マルバシモツケ ヒメシャジン



ゴゼンタチバナの実 ミヤマカタバミ ミヤマリンドウ



ミヤマガラシ キソチドリ ハハコグサ


キンコウカ ナナカマド紅葉出初め
![]()
![]()